見津毅さん没後20年で集会 ― 2015/06/07
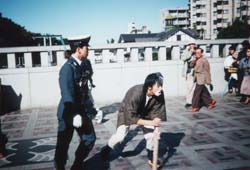





広島と長崎に行ってきました ― 2010/08/09

まあ、長年の経緯もあるからしょうがないかって雰囲気で行かせてもらっている感じだが、実際に全国の平和運動や反原発運動の活動家と情報交換したり、分科会の講師として呼ばれている先生方と意見交換するまたとない機会なんだよね。
今年は、臨時国会の日程と一部ダブり、議員会館の事務室の引越の準備とも重なったので、同僚のみなさんにだいぶ惑をかけてしまった。帰京の翌日(8月10日)の朝から引越だというので、僕の場合は出発前に自分の分の荷造りを終えておかないといけないということで、8月3日の深夜まで段ボールに資料をぶち込むという作業をして、強行日程で参加することになった。
議決権を行使した ― 2010/06/06
今年も株主273名が①配当を1株あたり100円(会社提案は60円)に引き上げる、②「核廃棄物の処分検討委員会」を設置して核廃棄物について責任ある対応を検討する、③「もんじゅ」開発協力からの撤退、④会社の目的にスマートグリッド事業を追加、⑤取締役の報酬等の公開、を提案している。
株主提案のすべてに取締役会は反対しているので、現状ではなかなか通る見通しは立たないけど、8号議案(取締役の報酬の公開)などは3年前に33%、2年前に27%、昨年26%の賛同がえられているらしい。こういう問題提起を続けることが大切、じゃないかな。
原発が事故を起こしたりすると、危険だわ、不安だわ、株価が下がってへそくりが減るわと、三重苦になるのでぜひとも安全に運転してほしいんだわ。
NPT再検討会議はじまる ― 2010/05/03

※95年NPT再検討・延長会議では3つの「決定」を採択した。①NPT延長に関する決定、②条約の運用検討プロセスの強化に関する決定、③核不拡散と核軍縮のための原則と目標に関する決定、である。
2000年のNPT再検討会議では、①CTBT早期発効及びそれまでの核実験モラトリアム、②カットオフ条約の即時交渉開始、③STARTプロセスの継続と一方的核軍縮の推進、④透明性の強化、⑤余剰核分裂性物質のIAEA等による国際管理と処分、等を明記した「最終文書」が採択することができたが、2005年のNPT再検討会議では01年の同時多発テロ以降の米ブッシュ政権の単独行動主義的政策の影響もあって合意に至らず決裂した。今回のNPT再検討会議では、オバマ米大統領が「核無き世界」を主張するなかで、前回2005年の失敗を取り戻すことが出来るのかが問われる重大な会議である。楽観はできないが、5日には中東非核化地帯創設をうたった中東決議の再確認を盛り込んだ共同声明を発表、これまで米国がCTBTを批准するまでは批准しないとしていたインドネシアがCTBTの批准手続に入ることを表明するなど、前向きな動きも出ている。オバマ政権が核無き世界を目指すと言っているこの機会を逃すことなく、核軍縮をドドッと前進させたいもの。
5・19 太田竜氏が死去 ― 2009/05/19

日本みどりの連合とかつくって86年の参議院選挙とか翌年の都知事選にでたのを見て、何なんだろうと思ってから、彼の主張をまともに認識しなくなったんだけど、頑張っていたんだなぁ。
MELTの寺岡衛さんと江藤正修さんが出した『戦後左翼はなぜ解体したのか』(同時代社刊)の別冊『資料集』のなかで、小島昌光さんが太田さんのことを書いていたのを、たまたまつい最近読んだのです。曰く「1週間に1回、400字詰めで10枚の原稿を書くが、書き始めから書き終わりまでほとんど修正がない。一気に原稿を書いても、起承転結がはっきりしている。ものすごい頭脳で、常人ではない」と。「放っておけば太田竜から原稿が次々出てくる」、「太田竜の頭の中に百科事典が入っている。知らないことが何もない。何かあると、それをすぐマルクス主義的に分析する。…全部知っている。即、論文が書ける。例えば○○問題で…論文を書けといったら、あっという間に書く。革命の戦略まで書いてしまう」んだそうな。
本当かよ?と思うけど、彼らは太田竜派の人々ではないから別にお世辞を言っているとも思えない。じゃあ、なんで革命出来なかったのよ?とかも思うけど、そんな人間が生きてるならぜひ一度、会ってみたかった。
フランスではLCR(第4インター)のオリヴィエ・ブザンスノーが大人気で「反資本主義新党(NPA)」を結成して大統領選のダークホースとなっているとか、日本でも政権交代があるかもしれないとか、JRCL(日本革命的共産主義者同盟)と「労働者の力」派が機関紙共同編集を決定したとか、激動の世の中をどう思っていたのだろう。
オバマ大統領は核政策を「チェンジ」できるか ― 2009/04/07

■原爆投下の責任を認める
まず第一に、オバマ氏は「核兵器を使用したことがある唯一の核保有国として、米国には行動する道義的責任がある」と、広島・長崎への原爆投下の責任を認めました。米国の歴代政権は原爆投下を日本の無謀な戦争を止めるため必要だったと正当化しており、これまで決してその責任を認めませんでした。オバマ演説はこの道義的責任を認め、核廃絶の「先頭に立つ」とはっきり宣言しています。そのことだけでも今回の演説は画期的だと評価したいと思います。
■脆弱なNPT体制
第二には、この新たな核政策がオバマ氏の個人的信念や理想に由来するだけではなく、米国にとって必然であったということす。
現在、核を規制する制度は核不拡散条約(NPT)しかありません。そもそもNPTとは、核兵器保有国が米ソ(当時)2国から英、仏、中と拡がるなかで、それ以上の核拡散を防ぐための妥協の産物として生まれました。67年1月時点で核兵器を保有していた米ソ英仏中を「核兵器国」として認め、その他の「非核兵器国」の核保有を禁じたのです。「核兵器がこれ以上拡がると大変なので核兵器は持たないことにしましょう。核兵器国もちゃんと核軍縮をしますから。非核兵器国の核開発を厳しく監視するかわり平和利用を認めます」という内容です。
この条約には当初から、5国だけ核保有を認めるのは不平等だという批判が浴びせらました。核兵器国はいっこうに核軍縮の義務を果たそうとはしないのに、非核兵器国はIAEA(国際原子力機関)の査察で厳格に縛られる。NPTに入らず核開発をする国も出てくる。非核兵器国にとってはNPTに協力する必要性が弱い、ごくもろい制度なのです。にも係わらず核の拡散を防ぐ仕組みは他にない。核保有国は核を独占し続けるためにはNPTを守り核軍縮の努力をしなくてはならないわけです。
さらに核兵器をめぐる状況が大きく変わりました。冷戦時代には米ソが互いに1万発もの核兵器を突きつけあうことで奇妙な安定が生まれました。このような核抑止の構造には、相手が一定の合理的・理性的な判断をするだろうというある種の信頼関係が必要です。しかし新たな核保有国が合理的な判断するかどうかは怪しい。核が抑止力としての役割を果たせるか分からなくなってきたわけです。まして国土や国民を持たないテロリストが核を持てば抑止もヘチマもありません。
■核抑止力から核不拡散へ
このような状況の中で、抑止力としての核の必要性よりも、核の拡散防止の重要性が高まって来たわけです。すでに冷戦終結後こうした議論がはじまっていました。96年にはリー・バトラー元米戦略空軍司令官ら世界の17ヵ国の元将官60人による核兵器廃絶を求める声明を発表され、98年にはカーター元米大統領など46ヵ国117名の文民指導者の声明も発表されました。その後、ブッシュ政権の単独行動主義政策の下で冷静な議論はすすみませんでしたが、07年にはキャシンジャー元国務長官ら米政界の重鎮4人による提言(フーバープラン)が出され、再びこうした動きがはじまろうとしていました。オバマ氏のプラハ演説もこうした流れの中にあるものです。冷戦型の核抑止力が有効性を失い、核不拡散・反テロのためにも核軍縮をすすめる必要が高まっているわけです。
■米国民が核を手放せるか
第三には、それでもなお道は険しいということです。
オバマ氏は、①ロシアとの核軍縮条約締結、②CTBTの批准実現、③兵器級核物質の生産停止条約交渉の妥結、など多くの具体的目標を掲げました。しかしどれをとっても実現は容易ではありません。なにより長年、核大国の位置に安住してきた米国民にとって核兵器は肯定的な存在だということです。オバマ大統領は米国民を説得することが出来るのか、そこがカギになるかも知れません。長年、核を振りかざしてきた米国の取り組みがどこまで世界の信頼を得られるかも分かりません。オバマ氏がこの困難な道をどう切り開くのか米国の核政策の「チェンジ」に大いに期待したいと思います。
1・27 ネバダ・デー ― 2007/01/29
最近ではあまり思い出されることも無くなりましたが、1月27日は「ネバダ・デー」です。アメリカのネバダ核実験場ではじめて核実験が行なわれてから今年で56年め。史上初の核実験は1945年7月16日にニューメキシコ州アラモゴードで行なわれていますが、1951年1月27日は第2次世界大戦を終えた、本格的な核時代の幕開けの日です。
世界の反核運動は、この日を「ネバダ・デー」と名付け、核実験の禁止を訴える機会として、核実験に反対する共同行動を繰り広げてきました。
広島や長崎では、今でも細々とした行動が組織されていますが、本当に「細々」。ヒロシマ・ナガサキ、ビキニの被爆体験を持ち、世界に核廃絶を訴えているはずの日本で、ネバダ・デーの存在自体ほとんど思い出されることはありません。
与党首脳や外務大臣が平気で核武装の議論すら持ち出すご時世ですから、やむを得ないのかもしれませんが、長年反核・平和にこだわってきた立場からすれば寂しいところです。
原水禁大会開幕 ― 2006/08/04
禁大会開会総会はそれぞれ4日と7日に開いて、連合の平和ヒロシマ集会・平和ナガサキ集会を5日と8日に開いていた。それを原水禁の総会をやめて、連合集会を4日と7日に移して、それまで連合集会の「共催」に名前を連ねていた原水禁と核禁会議を横並びの「主催」に格上げしたのが昨年。いろいろ批判があったなかで、そのスタイルを継続して定着させてしまったのが今年だ。原水禁大会参加者が全員参加する原水禁が主体的に担う場は、長崎大会「まとめ集会」のみになってしまった。
劣化ウラン兵器禁止国際大会 ― 2006/08/03
7・7シンポ関係…共同候補の現実 ― 2006/07/12
しかし、全国を見渡すと、共同候補が必ずしもプラスになるとは限らない例がたくさんあるのです。
分かりやすいのは青森県知事選の例。
●95年の青森県知事選 社民系候補が9・9万票、共産系候補が3・0万票。
●99年の青森県知事選 社民党候補が8・9万票、共産系候補が3・6万票。
●03年の青森県知事選 共同の候補(社民、共産、新社)が3・5万票。
03年の選挙の社民、共産、新社の共同の候補の平野良一さんは前回の共産党票にも及ばなかった。平野さんは元浪岡町長で長年にわたって反核燃運動を続けてきた人。高齢ではあったけど、人格・見識も申し分のない候補者だった。確かに告示一カ月前の決定で出遅れではあったけど、平野さんで共同候補でこんなボロ負けしたら、もうどうにもならないよって感じ。結局、この大敗北で旧革新勢力は総崩れになった。
このとき当選した木村知事がセクハラ不倫疑惑で当選後すぐに辞職して半年後(03年6月)に出直し選挙になるんだけど、社民党は候補者を出せず民主党と相乗り、共産党候補は1.9万票に止まった。
勝ったときしか報道されないから気付きにくいけど、共闘したら勝てるというのは実はウソ。沖縄はもともと革新が強くて、強いから勝ちに行く共闘が成立する。弱いのもが寄り添う形の共闘は実は多くが負けているのです。もちろんそれ以外にも様々な理由があるのだけど、まとまれば勝てるという大ざっぱな話ではなくて、勝てる共闘のために必要な条件を詳細にかつ具体的に考えていくことが必要じゃないか。
もちろん勝負自体には負けても、次に繋がる、あるいはそれぞれに持ち帰ってプラスになるような負け方にできれば、共同の意味は大いにある。しかし、結局、マイナス効果が残るような「共闘」も少なくないということも認識はしておくべきだと思う。
なお否定的なことばかり言っているようだけど、ぼく自身はあくまで革新共闘を推進する立場。ケチをつけて足を引っ張っているわけじゃありません。大ざっぱな善意だけの議論じゃなくて、緻密にプラスもマイナスも考えながら推進しましょうということです。


最近のコメント